Accumu Vol.5
モンタージュの魔術
早稲田大学文学部教授/映画評論家 岩本 憲児
編集とモンタージュ

スタンリー・キューブリック監督
「2001年宇宙の旅」(1968)
ワーナー・ホーム・ビデオ
スタンリー・キューブリック監督の『2001年宇宙の旅』(1968)には,猿人が棍棒(骨)をポーンと空に投げあげると,その骨は宙に舞い,ゆっくりと回転しながら,広大な闇に回転する宇宙ステーションへと形を変えるシーンがある。この映画の中でも忘れがたい,最も有名なシーンの一つである。

人類の夜明けを象徴するシーン。
この後猿人は空に向って骨を投げ上げる

宇宙ステーション
「取り合わせの妙」と言えば,物理学者でエッセイストでもあった寺田寅彦は,かつて映画のモンタージュ論について触れながら,日本文化には様々な形でモンタージュ的発想が見られること,日本料理や俳句などの「取り合わせの妙」もそうであると書いている。日本文化とモンタージュについては,1920年代にロシアのエイゼンシュテインが漢字・歌舞伎・和歌・浮世絵などに発見していった特徴でもあった。だが,ここでは文化全般に広げてしまうより,映像の領域で極めて大きな役割を果たしている。「編集」または「モンタージュ」映像の問題へ絞って話を進めよう。
様々な要素,部分,断片を集めて,あるいはそれらを合成して一つの組織だった形,あるいは全く新しい世界を構成する技法が編集である。映画の編集は映画理論史上,重要な問題や論争を引き起こしてきた。それはフランス語の「モンタージュ」という言葉を通してである。もともと,機械の組み立てや据え付けを意味したこのフランス語は,1920年代のロシアで映画の編集理論へと応用され,映画の組み立て方を考えるキーワードになった。日本語の「編集」という言葉は技術に傾きがちであるが,「モンタージュ」という言葉には美学や思想等,技術によって表現される内容への干渉を含んでいる。従って,私はここで,「モンタージュ」という言葉を使うつもりである。もっとも,現在の日本語化した「モンタージュ」は,一般には,正体不明の犯罪者を合成写真(いわゆる「容疑者像」)にして新聞やテレビで呼び掛けるのに使われる場合が多い。

「フォトモンタージュ」
(Thames and Hudson Ltd., London 1976)より。
ヒトラーのレントゲン写真
(体内はコインで一杯 1932)
モンタージュならぬ合成写真は,名画(絵画)の構図を模倣した「芸術写真」や心霊写真など,写真の誕生まもない19世紀にすでに登場している。芸術写真にしろ心霊写真にしろ,現実にはないイメージをこしらえて,見る人に感銘を与えたり,驚きを与えたりする。20世紀に入ると,いくつかの写真(あるいは写真と絵)を合成した絵葉書が出回るようになり,これまた現実にはない不思議な世界を作り出して人気を呼んだ。

木村恒久「キムラカメラ」表紙より
しかし,写真に「モンタージュ」という言葉が使われ出したのは,第1次世界大戦中に,ダダイスト達が「フォト・モンタージュ」を発表し始めてからだろう。ベルリン・ダダを中心とするフォト・モンタージュは,痛烈な批判精神を持ち,合成された写真像は社会の偽善性や腐敗した政治体制を風刺する強烈な媒体となった。このように,社会を撃つ武器としてのモンタージュ写真,欺瞞的人々を挑発するモンタージュ写真は,合成やトリックによって作り出されており,やはり現実にはあり得ない映像である。現代日本でもフォト・モンタージュは活力を持っており,例えば木村恒久のモンタージュ写真集『キムラカメラ』(注1)には現代文明に対するブラック・ユーモア,鋭い風刺と笑いが満ちている。
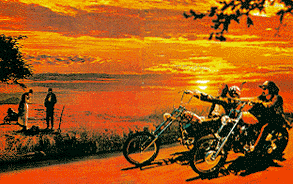
木村恒久「キムラカメラ」図23より
ダダイスト達が風刺や批判精神によってモンタージュ写真を社会に放ったとすれば,革命まもないロシアの構成主義者達,あるいはドイツのバウハウスの芸術家達は機械時代への積極的姿勢によってモンタージュ写真を発表した。彼らは時代や社会に対する批判よりも,新しい時代や世界への建設と再創造の意欲に満ちていた。従って,そこにはモンタージュの毒は消え,機械時代への明るい希望や信頼,人間の知覚と感受性への新しい挑戦が見られる。一方,ダダイスムと入れ代わるようにして起きたシュルレアリスムには,写真の持つ幻想や夢想への強い共感が見られる。現実性と幻想性―カメラ時代の映像(写真・映画・テレビ・ビデオ等々)には現実との密着感と,逆に現実から別の次元へ移行する幻想感と,二つの性格が同時に作用しており,これはカメラを使わないコンピュータ・グラフィックスが持つ現実感と幻想感へも通じている。
映画とモンタージュの実験

ルイス・ブニュエル+ダリ「アンダルシアの犬」(1928)より。
男の左手が女性の眼球を広げる。
男は右手に剃刀をもっている。
この後,月をスーッと横切る一筋の雲のカットが入り,
次にスーッと剃刀で切り裂かれる眼球のアップのカットとなる
シュルレアリスム映画の代表作『アンダルシアの犬』(ルイス・ブニュエル+ダリ,1928)は脈絡のない夢のような映像をつづる映画であるが,例えば最も有名な冒頭のシーン―剃刀を研ぐ男,満月の夜空,月をスーッと横切る一筋の雲,画面いっぱいの片目,眼球をスーッと切り裂く剃刀―もまたモンタージュによる衝撃的な映像効果を生み出している。それぞれ単独の画面は現実的な映像を見せているのに,一連の組み合わせが思いがけない効果をもたらすのである。もっとも,モンタージュは必ずしも衝撃的な映像を生むためだけの手法ではなく,本来的には映画の基本的な編集技法でもあり,その生み出す効果は多様である。古典的ハリウッド映画の基本は「見えないモンタージュ」もしくは「継ぎ目のないモンタージュ」にあるとされ,むしろ観客に意識されないモンタージュが好まれてきた。それは映画の物語の中へうまく観客を引き込み,心理的情緒的に同化させてしまうためである。
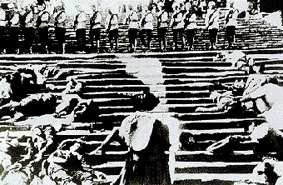

セルゲイ・エイゼンシュテイン監督「戦艦ポチョムキン」(1925)より。
有名な「オデッサの階段」シーン

ハリウッド映画のモンタージュが観客同化型であるとすれば,革命後のロシア映画には観客異化型とでもいうべきモンタージュ論が生まれた。その代表に『戦艦ポチョムキン』(1925)の監督セルゲイ・エイゼンシュテインと,『カメラを持った男』(1929)の監督ジガ・ヴェルトフがいる。エイゼンシュテインのモンタージュ論は「衝突のモンタージュ」と呼ばれたりするように,衝突もしくは対立・対照のコンセプトを画面接続・画面構成の基本にしている。画面接続というよりも画面切断と言った方がいいだろう。画面の連続性よりも,その非連続性が重視されるからである。非連続性によって観客の知覚を刺激し,違和感を覚えさせ,物語への同化よりも異化の働きを意識させることになる。
『戦艦ポチョムキン』の代表的なシーン,「オデッサの階段」を見てみよう。「突然」という文字(字幕)が入った後,女性の乱れた黒髪が画面を覆う。画面は一瞬のうちに,乱髪の数ショットから階段を駆け下りる群衆の下半身へ,前面を覆う白い日傘へと続いていく。そして階段をいざって下りる両足のない男性,姿を現す兵士の一団,階段で転ぶ眼鏡の女性,階段をなだれ下りる群衆,階段で倒れるズボンの男性の膝と脚,その倒れる人物の視点からか,ぐらつく視界,倒れる男性の膝と脚等々…エイゼンシュテインは時間・空間・被写体を分断して断片的映像でつづっていく。「乱れる黒髪」や「崩れ落ちる膝と足元」など,その切れ切れの断片性はとりわけこの「オデッサの階段」に際立っており,さらに対角線構図や動きの対立,線の対立(階段・直立する兵士達の足・投げかける影・向き合う母親・横たわる子供等,縦・横・斜めの線の交錯),リズムのはぐらかし(兵士達の歩調と画面接続の不同調),アクションの分割(時間空間の分割や引き延ばし)など,正しくこの作品が「モンタージュの映画」であることを思い出させてくれる。
エイゼンシュテインは映像の修辞法とでもいうべき様々なモンタージュ・タイプを考え出したり,視覚と聴覚を対立させたり(「視聴覚の対位法」)したが,それは観客の知覚の刺激を通して意識下の活性化や覚醒を狙ったからだった。エイゼンシュテインにとってモンタージュは単なる映画の技法にとどまるのではなく,観客の意識革命への手段,観客の意識を揺さぶる手段だったのである。(注2)この場合「観客」とは,映像を見る人すべてのことであり,当然,最初の観客は作者自身,エイゼンシュテイン自身のことにもなり得る。このような,映像知覚の問題,あるいは身体感覚まで含めた映像体験の問題は,バーチャル・リアリティの現象が広がりつつある現在,極めて現代的な課題設定だったと言えよう。一方,エイゼンシュテインの好敵手ヴェルトフはニュース映画や記録映画の領域でモンタージュの実験を行った。
付け加えておくと,映画のモンタージュは映像の展開の中(すなわち時間経過の中)が主になるが,一つの画面の中の場合もあり,そのとき画面には写真のように二重もしくは多重の合成映像が生まれることになる。
スクリーンとマルチ・イメージ


アベル・ガンス監督「ナポレオン」(1927)より。三面スクリーン
映像の連続性を切断することなく,視点の変化や複雑な構図を取ることを「画面内モンタージュ」あるいは「カメラ内モンタージュ」などと呼ぶことがある。これは空間の奥行方向を深く取ったり(ディープ・フォーカス撮影),カメラを長まわし撮影で移動させたりする方法によって成立する。時間・空間の連続性を保ったままなので,連続性を断つモンタージュよりも現実感があり,虚偽やトリック性が希薄であるように見える。もっともこの種の演出技術にも極めてトリッキーなものはあり,『爆音』(田坂具隆監督,1939)や『雨月物語』(溝口健二監督,1953)のように,カメラがゆっくりと360度のパン(水平移動)をし続けるうちに,時間が極端に経過していたり,次元の異なる人物が登場していたりするシーンもある。
映画は普通一つのスクリーンに映像を映し出すので,モンタージュは時間経過の中で行うか,画面の中(空間の中)で行うことになるが,もし複数のスクリーンがあれば,同時かつ同空間(複数スクリーンを一つの空間と考えて)の中でモンタージュを行うこともできるわけだ。映画史上よく知られているのは『ナポレオン』(アベル・ガンス監督,1927)の三面スクリーンだろう。巨大な三面スクリーンに広がる映像の展開とモンタージュ効果。三つの画面が別々のものを映すこともあれば,真ん中が別で左右対称,あるいは白馬にまたがったナポレオンが兵士達の前を,右のスクリーンから中央,そして左のスクリーンへとさっそうと駆け抜けて行くといった動きがあった。
複数スクリーンでなく,単一の大型スクリーンに複数映像を自由に映し出すやり方も,1960年代のニューヨークやモントリオール万国博以来盛んになってきた。そこにはいくつものスクリーン内フレームが自由に増加あるいは減少して,様々な映像の変化,生成消滅,類似と相違,運動と停止,単一化と複製化,融合と拡散を瞬時のうちに行うのである。
ビデオとCG
この種のマルチ・イメージ提示は,現在ではコンピュータを使ったマルチ・スライドやビデオ,CG等の電子映像に多用されるようになった。もっとも,複数のスクリーンではなく,単一の大型スクリーンでもなく,一般の劇場用映画の中で,フレーム内フレームを使う映画が登場している。それはハイビジョンによる合成映像を駆使した『プロスペローの本』(ピーター・グリーナウェイ監督,1991)である。これはモンタージュの新しい形と言えるかもしれない。
ハイビジョンの技術を使いながら,幻想的な合成映像を生み出した映像作家にズビグニュー・リブチンスキーがいる。新作は『オーケストラ』(1991)である。しかしここでは彼が以前に作ったビデオ作品を取りあげよう。『階段』(1987)というそのタイトルが暗示するように,エイゼンシュテインの『戦艦ポチョムキン』の「オデッサの階段」をパロディにしており,そのモノクロ映像のオリジナル・シーンに,現代のアメリカ人観光客が見物のために入り込むという面白い発想の作品だ。アメリカ人観光客達はカラーであり,モノクロの世界でもの珍しそうにオデッサの階段を上り始め,兵士達による市民の弾圧現場を「実地体験」することになる。時折彼らがつまずいたり,身体にショックを受けるのは,実は画面の切断部分,すなわちモンタージュによって継ぎ目ができている部分なのである。リブチンスキーの『階段』はビデオ・アートの分野に入るのだろうが,「モンタージュの映画」をさらに「モンタージュした」この作品は,オリジナル作品の最も特徴的な継ぎ目を残したまま,同一画面に異種の映像を挿入させており,写真的なモンタージュ概念を動く映像の中で奇抜かつ斬新な形で成功させたものと言えるだろう。
ハイビジョン技術と電子画像のけんらんたる姿は,『プロスペローの本』に現れている。ここでは,モンタージュの断片化と重層化が時間と空間の両方で対等になされており,画面内と画面連続双方の密度の高さはこれまでのフィルム系の映画にない複雑さを実現している。スクリーンのフレーム内に一つもしくは複数のフレームがあるシーンが多く,それはスクリーンを分割するというよりも,ちょうど同心円のように重なってずれた矩形をなしており,時に映像は別々のものを見せ,時に同じものを色調の違う薄いベールごしのように見せ,時に別々のものをオーバーラップで見せ,時には鏡を使ってさらに別の空間を反射させ,というふうに,フィルム画像と電子画像を重ね合わせた複合的イメージが次々に展開していく。この作品の複雑な画面,あるいは重層的な映像は正しく「電子時代のモンタージュ」と呼べるもので,単に技術的なレベルにとどまらず,時に美しく,時にグロテスクな,シェイクスピア原作の精神を新しい技術のもとに蘇らせた傑作である。
モンタージュの手法は,対象を操作するため,そこにトリックや虚偽性が入り込む。かつて,映画評論家の故アンドレ・バザンや記号学者クリスチャン・メッツらは,このような「操作精神」を嫌った。しかし,モンタージュは新しい意味や知覚や世界を創造する極めて現代的な手法でもあるのだ。
注
注1 木村恒久「キムラカメラ」(パルコ出版,1979)
注2 エイゼンシュテインの考え方とテクストについては,岩本憲児編「エイゼンシュテイン解読」(フィルムアート社,1986)参照



