Accumu Vol.1
火星の白雲の振舞い
斉藤 良一
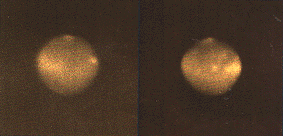
飛騨天文台65cm屈折望遠鏡により,青色光で撮影された火星のオリンパス雲。
左:1982年4月11日UT12時45分(オリンパス地方火星時11時56分)中央の白点がオリンパス雲
右:1982年4月8日UT14時49分(オリンパス地方火星時15時52分)左縁の白点がオリンパス雲
南が上,北極冠が下方に見えている。
提供 京都大学理学部飛騨天文台
火星の大気はたいへん薄いのであるが,白雲,霧,ダスト雲がしばしば発生し,雲の活動ははなはだ活発である。ダスト雲はすなわち火星の砂嵐であり,古くから黄雲と呼ばれて親しまれている。大きなものとしては1956年8月に発生して火星の南半球をおおったものや,1971年9月に発生して火星全球に拡がったもの,探査機バイキング号によって捕えられた1977年のものなどが有名である。特に1971年の黄雲は火星観測史上最大のものと言われ,ちょうど火星に到着した探査機マリナー9号は,当初ダストの雲海から突き出したオリンパス山とタルシス地方の三つの山の頂部を見ることができるだけであった。これに較べると白雲や霧は振舞いが穏やかで,火星の季節や昼夜のサイクルに応じて出現する。地上からの観測では,白雲や霧は青色光で撮られた写真に明るく写ってくる。火星の特徴とも言える地表の明暗模様は,もっと波長の長い赤色光の方で,場所による反射能の違いが大きいことに起因している。青色光では場所による反射能の差はほとんど無いので,地表の模様は通常はまず現れない。秋分から春分までの冬期に極地をおおう霧は極霧と呼ばれる。極霧はにぶい青灰色の雲で,この下で春分以降に明るく輝いて見えてくる火星の極冠が形成されていく。極霧は北極地方に形成されるものの方が南極地方のものより発達すると見られている。赤道から中緯度までの火星の縁や明暗境界線付近には,ぼんやり拡がった霧すなわち朝霧,夕霧が見られる。この霧は火星面上の特定の位置に結びついたものではないようである。これに対して火星面上の位置すなわち特定の地域に固定したはっきりした白雲もしばしば観察される。このはっきりした白雲の名所は,エリシウム地方(北緯25°,西経210°付近),タルシス高地(赤道上の西経110°付近を中心とする広大な地域),オリンパス山(北緯18°,西経133°)である。エリシウム地方にはエリシウム山,タルシス高地には3つの大火山があり,オリンパス山はもちろん標高26kmもある大火山であるから,白雲は地形性の雲であるといえる。タルシス-オリンパスの白雲は,よく発達したときには,個々の雲がつながってW字型に見えることもある。白雲は大きな地形にそって空気が上昇して冷やされるときに,空中の水蒸気が凍ってできる雲であると見られており,地球の雲にたいへんよく似たものと言える。北半球の春から秋にかけて発生し,特に夏の初めには非常によく現れる。また白雲は日変化を示すことも知られている。地上から観測すると雲は火星の昼近くに見えるようになり,午後の間中,縁に近づくにつれだんだん明るくなっていく。火星大気中の水蒸気量は平均して14ミクロン可降水量であるが,マリナー9号によるタルシス地方の白雲の赤外スペクトル観測によると,雲をつくっている氷は可降水量で0.5ミクロンほどの微量であった。また雲の光学的な厚さは0.4程度と見積られた。これは雲により光がe-0.4に減衰することを表している。白雲の中で少し変わっているのは南半球の中緯度にある大盆地ヘラスにかかるものである。ヘラス雲はオリンパス山などの白雲と異なり1日中明るさも変わらずに見えている。出現する時期はオリンパス雲などと同じであるが,半球が異なるので冬季の雲ということになる。
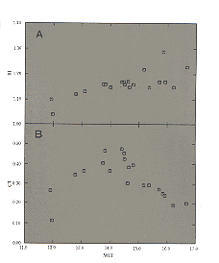
オリンパス雲の相対強度(RⅠ)と光学的厚さ(CT)の時間変化。
横軸は火星地方時(MLT)
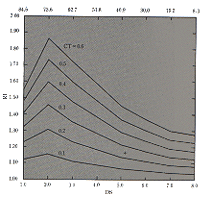
雲の相対強度(RⅠ)の光学的厚さ(CT)への変換。
横軸は反射光の流れの番号(DS)すなわち出射角
1982年3月と4月に京都大学飛騨天文台で撮影された火星写真に,オリンパス雲がよく写っている。雲は中心波長0.4ミクロンの青色光で撮られたイメージに最もよく現れ,火星の昼前から見えはじめて,夕方に縁に達するまでどんどん明るくなるという典型的な日変化を,観測された6日について繰り返した。このときの火星での季節はちょうど初夏にあたっていた。雲の中心はオリンパス山の山頂から北西に220kmほど離れたところ(北緯20°,西経137°)にあり,大きさは火星面上でおよそ5×105km2であった。われわれは青色光で撮られた良質のイメージについて,オリンパス雲と雲の外側の基準点のネガ上での濃度を測り,これらを輝度に引き直した。結果は図1Aで横軸に火星地方時,縦軸にオリンパス雲の基準点に対する相対強度をとって,6夜の観測をまとめて示してある。相対強度は時間とともに増加していくが,これはそのまま雲の発達を意味するとは限らない。雲の垂直方向の光学的厚さの変化が,真の雲の発達と減衰を表すことになる。したがって雲による反射光の強度を計算する必要が出てくる。これは輻射輸達方程式を数値的に解くことによって行える。雲は全体として平べったいものと考えてよいので,われわれは反射底面をもつ平板な大気中の雲粒子等による多重散乱問題をDOM(discrete ordinate method)と呼ばれる方法で解いた。DOMによると輻射輸達方程式は半解析的に精度よく解くことができる。われわれは輻射の方向を16個の流れに分けた。したがって16次行列の固有値問題を扱うことになるが,値の小さな固有値のときに生じる数値計算上の不安定の対策が施してある。雲は水の氷と見られるから,球粒子を考えるミー散乱の場合や,近年得られるようになった非球形氷晶の実験値の場合などの散乱特性を用いて計算を行った。雲の他にも火星大気によるレーリー散乱,つねに大気中に浮遊していると見られるダストによる散乱がとり入れられている。ここでも氷晶やダストのように強い前方散乱を示す粒子の散乱の位相関数の扱いに計算上の工夫がしてある。雲粒子は6.2mbの炭酸ガス大気(光学的厚さ0.01)に,光学的厚さ0.4のダストとともに一様に混じっているものとした。また地表面は反射能0.06で等方散乱をすると見なした。雲の光学的厚さをパラメータにして理論的な反射光強度の角度分布,したがって相対強度分布が計算され観測と比較される。図2は氷晶の実験の散乱特性を用いた場合の一例で,図1Aの右から三つ目の観測データを処理している。縦軸は相対強度,横軸は外方へ向かう輻射の8個の流れで,上に出射角(天頂角)に直したものも示してある。実際の太陽光の入射角54.1°のもとでの反射光の相対強度が雲の光学的厚さ0から0.6まで0.1ステップで計算してあるから,実際の反射光の出射角38.5°,相対強度1.17の点(+印)に合う雲の光学的厚さは,補間して0.25ということになる。ちなみにこの一例で計算時間は京都大学大型計算機センターのFACOM M783で3秒,京都大学花山天文台のDEC VAX11/750で12分ほどである。氷晶の実験からの散乱特性を用いた場合について,このようにして得られたオリンパス雲の光学的厚さが図1Bに示されている。ここで縦軸は雲の光学的厚さである。オリンパス雲は昼前に見えはじめ,次第に発達して午後2時頃に光学的厚さの最大値0.5に達し,その後はだんだん減衰していくことがわかる。雲が最も発達したときの氷の量は,可降水量にして0.7ミクロンほどと見積られる。
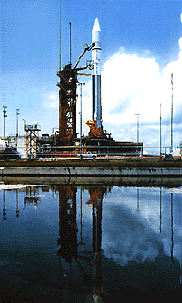
NASA提供
この雲の光学的厚さはマリナー9号の観測値0.4によく一致している。ただしマリナー9号はタルシス高地のアスクレウス山にかかる雲とまわりの雲のない部分を同時に見込んで観測しているので,アスクレウス雲の厚さはもっと大きいと見られている。アスクレウス山はタルシス地方の三つの山のうち最も北にあり,オリンパス山とは高さや緯度の条件がたいへん似通っている。またバイキング1号軌道船による赤外スペクトル観測では,オリンパス雲の光学的厚さが1かそれ以上であるらしいと報告されている。われわれの地上観測でもマリナー9号の観測に似た状況が考えられ,得られた値は良好であると言える。1982年の3月と4月に現れたオリンパス山の白雲は,この雲のたいへん出やすい時期の普通の発達度のものであったと見ることができる。白雲の出現する時期や日変化の度合いが年によってどのように変わるかということが次に興味がもたれる点である。現在のところ細かい年変化を議論するほど十分な観測データは集積されていない。ねばり強い地上観測,解析法の進歩,新たな直接探査など今後の研究に期待されるところが大きい。



