Accumu Vol.7-8
海外コンピュータ教育支援活動 ペルーへ
京都コンピュータ学院 村上 俊也
1.出発

ペルー国旗
阪神大震災のすぐ後の1995年1月22日,私達は震災の衝撃に揺れる日本を後にした。ペルーまでは関西国際空港から,ロサンゼルス,マイアミ経由で24時間の道程であった。ペルーの首都リマにあるホルヘ・チャベス空港に到着したのは,早朝の5時半。空港のロビーでペルー共和国教育省の方々が日本から来た私達を笑顔で出迎えてくれた。空港の建物を出ると,朝まだ早いのにもかかわらず,すでに日差しが強かった。その日差しを浴びながら,私は,日本を出発した時の,肌寒さを思い出していた。そして,地球の反対側に来たのだということを強く実感した。

ペルーという国は,19世紀初頭までスペインの植民地としてその圧政を受けていたが,1821年,サン・マルティン将軍の指導のもとペルー共和国として独立した。現在の大統領は日系2世のアルベルト・フジモリ氏である。ペルー共和国は日本の約3.4倍の土地に約2400万人の人々が生活している。国土の約60%が森林地域,約25%が山岳地域で,そこは豊富な鉱物に恵まれ,ペルーの主な産業を作り出す宝の山となっている。
日本から見て,地球の反対側に位置するペルー共和国。この国に,私達は京都コンピュータ学院海外コンピュータ教育支援活動の一環として,ペルー政府が国内に情報処理教育を広めるにあたっての支援をするために訪れたのであった。
2.ペルーでの生活

私達のペルー滞在期間は2週間であった。私達はペルーの高等学校や大学の先生方を対象とするコンピュータ講習会に講師として参加した。講習会はリマ市内の高等学校で行われた。そのため私達は滞在期間の大半を首都リマで過ごすこととなった。
リマはペルーの人口の約3分の1が住む大都市である。リマの郊外には砂漠が広がり,更にその外には広大な熱帯雨林が広がっている。リマはもともと,熱帯雨林の中の砂地に作られた町である。市内の交通量は非常に多く,米国製自動車や,ドイツ車のフォルクスワーゲンをよく見かけた。フォルクスワーゲンは特に台数が多く,私の見かけた車の4割程度を占めるほどであった。ただ,走っている自動車はお世辞にもきれいなものとは言えず,古いものが多かった。ビジネス街に行くと,近代的なビルが立ち並び,日本企業のビルの大きさが目立った。その一方で市内のところどころにスペイン統治時代の名残であろうか,重厚な石造りの教会がそびえている。日中の温度は年間平均して30度前後であり,日差しが強い。また年間を通じてほとんど雨が降らない。そのため,乾燥した街中では,Tシャツに短パンという軽装の人々が多かった。
ペルーでの食生活について一言触れておくと,セビッチェという酢づけの魚料理が有名である。日本で言うところの魚のマリネに似た食べ物である。またマンゴやパパイヤなどの果物が非常に豊富であった。私達はこれらを「インカコーラ」という名の炭酸飲料とともに食べた。
3.講習会
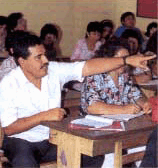
今回のコンピュータ講習会は,講師として日本から来た学院職員の私達3名の他,米国の大学MITからの1名,更にペルーからは講師兼通訳としてフジモリ大統領の姪であるイリアナ・フジモリさんが参加した。
そして受講生は先に述べたとおり,ペルーの高等学校や大学の先生方であった。こうした顔ぶれからもわかるように今回の講習会は,様々な文化圏の方々が集い,国際的な雰囲気の中で行われた。
初めは,それぞれの文化の違いから講習会が計画どおりに運ばないということもあった。講習会の計画は私達が日本にいながら立案したものであった。私達は講習会を午後5時まで行うという前提でスケジュールを立てた。ところが,ペルーの人々はおおむね午後3時以降は働かない習慣であることが後にわかった。実際にペルーに来てみると,午後2時くらいに昼食をとり,その後はシエスタに入る。「シエスタ」とは,「午後の休息」である。具体的に言えば,昼寝をするのである。スペイン植民地時代の名残であろうか。日本ではなかなか信じられない習慣である。しかし,ペルーにいて午後の強い日差しを浴びていると,こうした習慣の必要性も実感できる。
また,講習会が始まって暫くたったある日,講習が終わってから,受講生の1人が近寄って来て,「明日は多分,来る人があまり多くないかもしれないね。」と言った。理由を尋ねると,その人は「明日は給料日だから。」と答えた。私は耳を疑った。よく話を聞くと,給料日には仕事を休むことが多いのだそうだ。これも日本では考えられない習慣である。
私は,最初の頃,講習会が予定どおりに進まないことに苛立ちさえ覚えたが,次第に,これがペルーの文化なのだと気づいた。それとともに,ペルーの人々のおおらかとも言える文化の方が日本人のあくせくした生活よりも人間にとって好ましいものかもしれないと思うようにすらなっていった。
受講生であるペルーの先生方からは,最先端コンピュータ技術を自分のものとし,更にその技術を自分達の教え子に伝えたいという情熱が強く感じられた。例えば,毎日の講習では受講生からの熱心な質問が相次いだ。1人が質問をすると,それに続き何人もの受講生が幾つもの新たな質問をしてくる。そのため講習をする私達にも自然に熱がこもってきた。
また,やはり言葉の壁は歴然とあったが,たとえ言葉が通じなくても,ペルーの人々は目が合うと必ずニコッと笑顔を見せてくれ,必ず何かスペイン語で一言言葉をかけてくれた。その言葉の意味はよくわからなかったが,ペルーの人々がそのように接してくれるおかげで,地球の反対側の文化の異なる国へと来た私達の不安は取り除かれていった。
このように講習会はとても活気に満ちたものとなり,単なる技術交流を超えた,心の交流を実現することができた。
4.休日
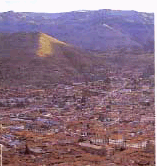
講習会の合間の休日に私達は,ペルー第2の都市クスコを訪れた。クスコの街は石畳の美しい高原の街であった。アルパカという名の首の長い羊に似た動物が,街中の路を民族衣装を身にまとった女の子にひかれて歩いていく。喧噪に満ちたリマと異なり,クスコの街には伝統と歴史の重みを感じさせる静けさが漂っていた。標高3300mにある街であるためか,人々の動きもゆったりとして見えた。高原に慣れない私達にとっては歩くだけでも息が切れて苦しいほどであった。
この街はかつてインカ帝国の都であった。そのためか,リマでよく見かけるスペイン系の顔立ちと明らかに異なるインカの末裔と思われる顔立ちの人に数多く出会った。
インカ帝国は1532年にフランシスコ・ピサロ率いるスペイン人によって征服される。全盛期には,その領土はエクアドルからボリビア,チリにまでおよぶ南米最大の大帝国を築いていた。
クスコはその大インカ帝国の中心であった。
現在,この地方の言葉はスペイン語が主であるが,インカ帝国時代はケチュア語という言葉が使われていた。クスコでは現在でもケチュア語が準公用語で街中のいたるところで耳にすることができる。
私達はクスコの郊外にある,インカの遺跡,マチュピチュへと足をのばした。マチュピチュはクスコからバスと高原列車を乗り継いで約3時間程度のところにあった。
小高い山の頂上に作られた街。そして,ある日突然歴史の上から姿を消してしまった街。
マチュピチュの特色は石積み建築の素晴らしさにある。実際に近寄って触ってみると,カミソリの刃も通さないほど,隙間なく1m四方もの巨石がきれいに積み重ねられている。一体どのような方法で,このような緻密な建築は可能となったのだろう。しかも建築の作業が為された場所は,猫の額ほどの広さの山の頂上である。私はこの遺跡に立ちながら,悠久の時を超えて,かつてここで暮らしていたインカの人々へとしばし想いを馳せた。
5.終わりに
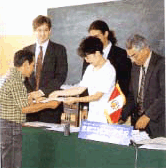
講習会最終日。受講生の講習会における努力と成果を讃え,学院から受講生一人ひとりに対して修了証書が授与された。修了証書を手にした受講生達の顔には達成感が満ち溢れていた。その笑顔を見て私は,私達がペルーで過ごした2週間を,この国の人々にとっても,私達自身にとっても意義深いものとすることができたと確信した。
ペルーを発つ日,空港には大統領府勤務の大統領の実弟フジモリ氏が多忙の中にもかかわらず見送ってくださった。こんな歓送は例がないそうで,私達の行った講習会がいかに重視されていたかをあらためて実感した。



