Accumu Vol.1
火星の極冠を計算する
岩崎 恭輔
火星の極冠
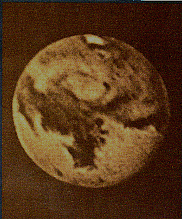
CCDカメラにより撮影され,画像処理された火星の赤色像
1988年10月3日UT7時52分,
アリゾナ大学のS.LarsonとG.Rosenbaumが
カタリナ天文台の1.54m望遠鏡により撮影。
南極冠が上方に見えている。
提供 アリゾナ大学月惑星研究所
火星の北半球の冬の間,北極地方は一面極霧におおわれており,地表面はほとんど見えない。しかし,春分の頃になるとこの極霧が突然晴れ上がり,その下から真っ白に輝く極冠が見えてくる。極冠は春から夏にかけて縮小し,夏至頃になるとそれ以上縮小しなくなる。秋分の頃になると,北極地方は再び極霧におおわれてしまい,地表面が見えなくなる。一方,南極地方の極霧は,ヴァイキング2号の観測によると,冬至をすぎてから突然現れ,北極地方のものにくらべると厚さも薄く,場所的にも時間的にも極地方全体をカバーしていない。この極霧が晴れ上がる時期は北極地方の場合と同様春分の頃である。しかし,極霧の下から顔を出した南極冠の大きさは北極冠にくらべるとかなり大きい。これは,火星の公転軌道の離心率が大きいためである。すなわち,火星は南半球の冬には太陽から一番離れた遠日点付近にいるので,比較的遅く公転する。したがって,南半球の冬は北半球の冬にくらべると寒くて長くなる。このため,春分の頃に見える南極冠は北極冠より大きくなるのである。南半球の夏には近日点付近を通過するため,太陽からの入射エネルギーが多くなり,南極冠の縮小するスピードは北極冠より速くなる。また,夏でも解けずに残っている永久南極冠は,永久北極冠の1/3まで縮小してしまう。
火星は2年2ヵ月ごとに地球に接近するが,火星の公転軌道の離心率が大きいため,軌道上のどこで接近が起こるかによって,地球-火星間の距離が倍近くも違ってくる。近日点付近で接近が起こると,火星は地球に5600万kmまで接近し,大接近と呼ばれる。最近では1986年と1988年が大接近であった。地球の自転軸は23.5°傾いているが,火星も同じように自転軸が25°傾いている。このため大接近の頃は火星の南半球が地球の方に傾いており,南極冠の縮小が観測できる。一方,遠日点付近の接近では,地球-火星間の距離は倍近くの1億kmにもなり,小接近と呼ばれている。1995年がこれに当たる。小接近の時には火星の北半球が地球の方に傾いているため,北極冠の縮小が観測できる。
火星観測と極冠の測定
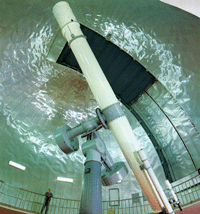
65cm屈折望遠鏡 提供 京都大学理学部飛騨天文台
京都大学花山天文台では1956年以来,当学院の名誉学院長の宮本正太郎先生を中心としたグループによって,45-cm屈折望遠鏡を用いて火星の連続観測が行われており,1971年からは京都大学飛騨天文台でも65-cm屈折望遠鏡を用いて行われている。1986年と1988年の大接近の時には,日本にくらべて観測条件の良いインドネシアのボスカ天文台との協同観測が,当天文台の60-cm二連屈折望遠鏡を用いて行われた。
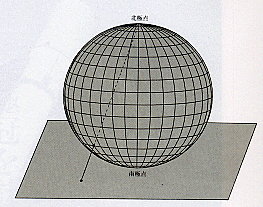
図1 ステレオ投影の定義
われわれは赤色光,橙色光,黄色光,緑色光で撮影された良質のイメージについて,極冠の大きさを測定した。球面三角法の方程式を用いると,測定した極冠の大きさから極冠の緯度,経度を計算することができる。われわれはFORTRAN77でプログラムを組み,花山天文台のDEC社製VAX11/750で計算を行っている。測定した値を入力すると,一瞬のうちに計算された緯度,経度がディスプレーに出力され,同時にデータ・ファイルに書き込まれるようになっている。春から夏にかけての北極冠の形は北極点に対して対称である。しかし,南極冠の場合は,春先は南極点に対して対称であるが,季節が進むにつれて南極冠の形の中心は南極点からずれてくる。すなわち,南極冠の端の緯度は経度によって異なってくる。したがって,南極冠の場合には,南極冠の大きさを単純に南極冠の端の緯度でもって表すことができない。そこでわれわれは南極冠の形が円であると仮定して,その円の半径でもって南極冠の大きさを表すことにした。このために,球面を平面に投影するステレオ投影を用いている。北極点から光を当て,極冠の端の位置を南極点に接する平面に投影するのである(図1)。この方法により,極冠の端の緯度,経度を平面上の直角座標に変換することができる(図2)。図で白丸は南極冠の端の測定点を示している。これらの測定点に最も良く合う円を最小自乗法を用いて計算する。得られたデータはXYプロッターまたはカラー・グラフィック・ディスプレーに出力されるようになっている。
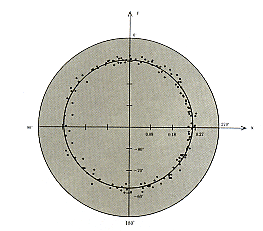
図2 ステレオ投影で表わした火星南極冠の形。
原点は南極点,y軸は経度0°,x軸は経度270°に対応する。
極冠の端の測定点が白丸,
測定点に最も良く合う円が実線で示されている。
1988年の南極冠の縮小
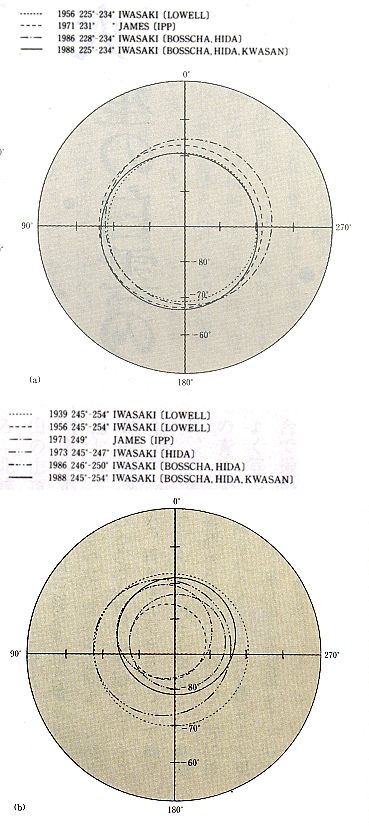
図3 各Lsにおける1988年と他の年の南極冠の比較
1988年の南極冠が春分頃から夏にかけて縮小していく様子が図3に示されている。Lsは火星中心太陽経度で,火星の季節を表している。Ls=0°が南半球の秋分,90°が冬至,180°が春分,270°が夏至に対応している。年による違いを見るために,他の年の南極冠の様子も一緒に示されている。Ls=225°-234°までは,図3(a)に示されているように,南極冠の大きさは年によってあまり変わらないようである。しかし,Ls=245°から254°あたりになると,図3(b)に示されているように,1988年の南極冠の大きさは1956年,1971年,1973年より大きいが,1939年,1986年より小さいようである。以上の結果をまとめた南極冠の縮小の年による違いが図4に示されている。1988年の南極冠の縮小は比較的遅かったようである。
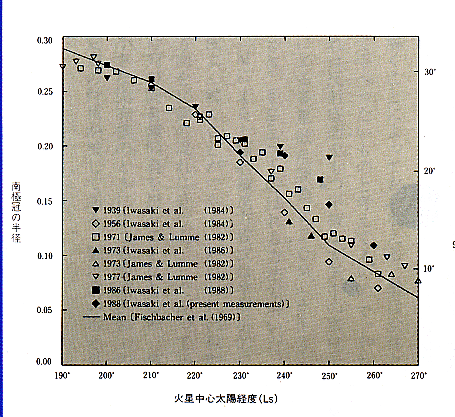
図4 南極冠の縮小の年による相違
極冠の縮小の年変化
宮本先生は花山天文台での眼視観測から,1973年の南極冠の縮小が1971年のそれに比べて速かったことを報告されている。われわれは1973年に飛騨天文台で観測された写真を測定し,1907~1956年のローエル天文台のデータから求めた南極冠の平均の縮小曲線と比べてみた。その結果,1973年の南極冠の縮小が平均より速いことを求め,宮本先生の結果を裏付けた。1907~1956年のローエル天文台の南極冠の大きさの測定を,われわれが再調査した結果でも,南極冠の縮小の様子が年によってかなり異なっていた。北極冠の縮小についても年変化があることが,宮本先生やわれわれによって示されている。
このような極冠の縮小の年変化の原因は何であろうか。ヴァイキング軌道船が撮影した1977年の南極冠の写真の解析から,1977年の南極冠の縮小が例年に比べて遅いことが示され,その原因としてLs=205°に発生した大砂嵐が考えられている。大砂嵐によって巻き上げられたダストが太陽エネルギーを吸収したため,南極地方に達するエネルギーが減少し,極冠の縮小が遅くなったというのである。
大接近の時は火星は近日点付近にいるので,太陽からの日射量が最大となり,大黄雲(火星上では大砂嵐)が発生しやすい。1956年や1971年の大接近の時にも大黄雲が発生している。したがって,1986年と1988年の大接近の時も大黄雲の発生が期待されたが,なぜか大黄雲は起こらなかった。1939年の大接近の時にも大黄雲は起こっていない。Ls=250°における南極冠の大きさと黄雲の発生時期の間の関係を調べてみたところ,大きくふたつのグループに分けられることがわかった。Ls=250°における南極冠の大きさの大きい1924,1939,1986,1988年のグループは小,中規模の黄雲は発生しているが,大黄雲は起こっていない。一方,Ls=250°における南極冠の大きさが比較的小さい1956,1971,1973,1977年のグループはいずれも大黄雲が発生している。したがって,Ls=250°での南極冠の大きさが大きい年は大黄雲が発生しにくく,南極冠が小さい年は大黄雲が発生しやすいのではないだろうか。1971年の大黄雲はLs=260°で発生しているので,大黄雲がLs=250°以前の南極冠の大きさに直接影響を及ぼしたとは考えにくい。1977年のヴァイキングの観測では,南極冠の大きさと大黄雲の間には因果関係が見られたが,それ以外の年では南極冠の大きさと大黄雲の間には明白な因果関係はなさそうである。南極冠の大きさと大黄雲の発生の両方を支配するような気象要素が存在するように思われるが,それが何かは解っていない。これらの問題を解決するためには,さらに多くの地上望遠鏡及び探査機による観測データが必要と考えられる。
CCDによる火星観測
1988年の大接近の時には,フランスのピク・デュ・ミディ天文台,アメリカのアリゾナ大学のスチュアード天文台,日本のアマチュアグループなどによって,CCD(電荷転送素子)カメラによる火星観測が行われ,すばらしい映像が得られた。CCDカメラからのコンポジットビデオ信号はコンピュータに取り込まれ,イメージがデジタル化されるので,画像処理などの作業が比較的簡単に行える利点がある。また,CCDカメラは感度が良いため露出時間は1/10~1/30秒ですみ,写真より1オーダ程速い。望遠鏡で見た火星はコントラストが弱く模様が見えにくいが,CCDカメラで得られたイメージはコントラストが強く模様が見やすい。このように多くの利点を持ったCCDによる火星観測に大きな期待がよせられている。



